 |
|
大佑 一周忌追悼公演「漆黒の光」 2011年7月15日(金)  
1.I think I can fly 2.夕暮れの謝罪 3.Break Down 4.evolution 5.Never ending story 6.再会
1.迷走本能 2.「6」party 3.my room agony 4.浸色 5.サイクロン 6.LOVERS
1.シュレーディンガーの猫 2.d.CHILD 3.PicaSSo 4.奈落に咲く 5.Howling
1.大嫌い 2.絶望 3.娼婦 4.パノラマ 5.咆哮 6.蘭鋳 7.リブラ
2.sweet powder 3.さよなら雨(レイン) 4.ハーメルン 5.ジャパニーズモダニスト 6.消毒

1.嫌 2.グリード 3.地下道に流れる、ある独りの男の「悲痛な叫び」にも似たメロディー 4.独裁者の涙 5.翻弄 6.葬送
1.raindrop 2.after this introduction 3.スパイダーネスト
1.絶望にサヨナラ 2.縄 |
午後1時半、通常のライヴとはどこか違った種類の空気に包まれた場内がゆっくりと暗転すると、ステージ脇のスクリーンに浮びあがったのはギルガメッシュのロゴ。スポットライトのなかで左迅が歌い始めたのは「I think I can fly」。若々しいカラフルさと躍動感を持つこのバンドだが、この日のパフォーマンスの滑り出しは、しっかりと地に足の着いたもの。冒頭から、成長というよりも成熟ぶりを感じさせた。このバンドのベーシスト、愁が、過去に蜉蝣のローディを務めていた事実を知るファンは少なくないはずだ。2曲目は「夕暮れの謝罪」。言うまでもなく蜉蝣の代表曲のひとつだが、これは単なるカヴァーではない。愁自身の説明によれば、これは「このメンバーで初めて合わせた曲」でもあるのだという。いわばギルガメッシュは、蜉蝣をバンドとしての出発点としていたわけである。まさに大佑ばりの絶叫でこの曲を演奏し終えると、すでに一体感のなかにいた観衆を束ねたまま、4人はポジティヴ・チューンを連発。最後は「再会」をじっくりと聴かせながら密度濃いステージを終えた。 幕間には蜉蝣やthe studsのミュージック・クリップがスクリーンに浮かび、観客はその場から流れ出ることなく一部始終を見届けようとする。そして午後2時20分、二組目の出演者として登場したのは12012。「新木場、行こうぜ!」という扇動の声とともにまず炸裂したのは「迷走本能」。これまた言うまでもなく蜉蝣の楽曲だが、瞬時にしてカヴァーとは気付かぬほど、その世界観が12012によく似合っていた。この曲の歌詞に顔を出す「君の最後の言葉、今も耳に残り」、「自分傷付けたって何も変わらないと知っているさ」というフレーズが胸に突き刺さるのを感じたのは、筆者だけではないだろう。その後は、このバンドを象徴するキラー・チューンを惜しみなく重ねながらの波状攻撃を展開。まだ4人編成になってからのライヴ歴は浅い彼らだが、新たな体制で繰り出される「浸色」や「サイクロン」は従来以上にロック然としたスケール感を持ち合わせていた気がする。フロントマンの宮脇渉は、まるで大佑の声を求めるかのように何度もマイクを天に掲げていたが、このバンドの進化も確実に彼のもとに伝わったことだろう。最後の最後は、他ならぬ大佑に捧げられた「LOVERS」。喉をかきむしりながら泣き叫ぶような歌声が心に響いた。 三番手としてステージに登場したのはboogiemanだ。暗転した場内に響く電子的なビートに順応しながら、メンバーたちが姿を見せる前から場内には手拍子が自然発生。サビのせつないメロディが印象的なオープニング・チューン、「シュレーディンガーの猫」でオーディエンスの気持ちをつかむと、ヴォーカリストの柊が堂々と最前線に立ちながら「今日は大佑さんも観ててくれると思うし、俺は全力で歌って、全力で届けたいと思います!」と宣言し、「だからみんなも全力で声を出して!」とオーディエンスを挑発する。次なる「d.CHILD」では確実に一体感を手に入れ、曲を重ねるごとに加速。ヴェテラン揃いのプレイヤー陣は手堅くもワイルドな演奏を聴かせ、蜉蝣時代の大佑の同胞であるギタリストのユアナは、明るく開放的なムードの漂う「Howling」でこの日の演奏メニューを締め括ると、口に含んだ水を客席に向けて噴射してみせ、ローディに向かってギターを投げ捨てるようにしながらその場を去って行った。 ふたたび幕間のミュージック・クリップ上映を挟み、BGMの止んだ暗い場内に聴こえてきたのは、瞬時にして空気の色を変えてしまう、お馴染みのSE。スクリーンにムックの朱いロゴが映し出される。そして、手拍子でメンバーたちの登場を待つオーディエンスの耳にまず飛び込んできたのは、アタックの強いベースの音。いきなりの「大嫌い」だ。着物に身を包んだ逹瑯が、ダイナミックな動きで観衆の目を釘付けにすると、その背後ではミヤとYUKKEが猛スピードで交錯する。しかも血気さかんな観客は、早くもクラウドサーフに興じている。まさにSTUDIO COASTが巨大アリーナと化したかのような錯覚をもたらす光景だった。このバンドと蜉蝣、逹瑯と大佑の縁の深さについては改めて説明するまでもないはずだが、この日の彼らは敢えてありがちな追悼メッセージを発するようなことをせず、努めて通常通りのムックのライヴを完遂しようとしているように感じられた。ただし、"あの頃"の楽曲を随所に配した演奏内容には当然ながら大佑に対する気持ちが込められていたはずだし、「騒ごうか!」という通常通りのMCに続いて逹瑯の口から発せられた「思いきり楽しそうにして、呼び込んじまおうか!」という言葉にもグッとくるものがあった。彼が客席に向けて手を振り、深々と礼をして姿を消す頃には、時刻は4時半をまわっていた。 続いてステージに登場したのは、ムックと同様、蜉蝣と"あの時代"に御三家の一角を担っていたMERRY。ミステリアスなSEに乗って幕が開くと、すでにメンバーたちは配置に。ガラの「新木場、踊れ!」という叫びに導かれて始まった「不均衡キネマ」の即効性の高さはこの日も有効に発揮され、フロアの熱はそれまで以上に上昇。続く「sweet powder」を歌いながら、ストリップのごとく上着とネクタイを脱ぎ捨てたガラの口から発せられた「彼が好きだった曲、やります」との言葉の後、一瞬の静寂を挟んで聴こえてきたのは「さよなら雨(レイン)」だった。この曲を歌っていたとき、ガラがシャツの袖で拭っていたのが汗だったのか涙だったのかは定かではないが、観衆の声援には間違いなく涙声が混じっていたように思う。しかしステージ後半、彼らはそうした空気を断ち切るかのように、攻撃的チューンの連発で会場全体を激しく揺さぶってみせた。ことにガラが大佑に呼びかけるように発した「聞こえるか!」という叫びに呼応しながら会場全体が大合唱となった「ジャパニーズモダニスト」の一体感は見事なものだったし、そのガラが「お前らみたいなクサったやつらは消毒だ!」とシャウトし、CO2をまき散らしながら炸裂させた「消毒」の破壊力にもすさまじいものがあった。 こうした盟友たち5組の演奏終了後、場内にはある種の不穏な空気が流れていた。このイベントがこの先、どのように展開されることになるのかが、誰にも読み切れなかったからだろう。冷淡な言い方に聴こえるかもしれないが、なにしろこのMERRYのステージをもって"現存するバンド"のライヴ・パフォーマンスはすべて終了しているのだ。 午後5時39分、ふたたび暗くなった場内に突然響いたのは、不気味な鐘の音。歓声とどよめきが入り交じったノイズに一帯が包まれる。大佑と黒の隠者達。その邪悪な世界がこれから繰り広げられようとしている。しかし当然、大佑はここにはいない。果たしてこれから何が起ころうとしているのか? 誰もが固唾を呑みながら、黒装束のメンバーたちが演奏をスタートさせるのを待っている。すると始まったのは「嫌」だった。歌っているのは、スクリーンのなかで生きている大佑だ。映像のなかの彼は「早く俺を消してくれ/君が俺を消してくれ」と懇願する。もちろん誰も彼が消えてしまうことなど望んではいないが、あっという間にこの曲は着地点を迎えてしまう。 すると、いつのまにかステージ中央に、12012の宮脇渉の姿があった。曲はもちろん、彼が『漆黒の光』のなかでヴォーカルを担当していた「グリード」。大佑がヴォーカルを録ることがないまま未完の状態にあったこの楽曲が、このアルバムでは宮脇によって生命を吹き込まれている。同様にして、続く「地下室に流れる、ある独りの男の「悲痛な叫び」にも似たメロディー」ではMERRYのガラが、「独裁者の涙」ではムックの達瑯が登場。大佑がそこに憑依しているかのように感じられる部分もあったが、それ以上に、誰もが楽曲を自分のものとして消化している事実が興味深かった。そしてさらに大佑と黒の隠者達のステージは、ふたたび大佑の映像を交えながらの「翻弄」を挟み、DIR EN GREYの京を招いての「葬送」で幕を閉じた。京の思いがけぬ登場に観衆はすさまじい熱狂をみせたが、その図に誰よりも驚かされていたのは天上の大佑だったに違いない。 果たしてこれ以上の何かが起こり得るものなのか? 大佑と黒の隠者達の究極的ともいうべきステージ終了後、誰もがそう感じていたことだろう。が、場内の熱はその後も一瞬たりとも冷めてしまうことがなかった。次に登場したのはaieとyukino、そして響。そう、the studsである。ステージ中央、大佑が立つべき場所には主を失ったマイクスタンドがたたずみ、「raindrop」がaieによるヴォーカルで披露される。続くインストゥルメンタル曲、「after the introduction」に牽引されるようにして始まったのは、生前の大佑にとってのフェイヴァリット・ソングだった「スパイダーネスト」。ライヴ映像を交えながらの生々しいパフォーマンスを前傾姿勢のまま終了すると、メンバーたちは往年のライヴのときと同様、仰々しさとは無縁のまま潔くきっぱりとステージから姿を消した。 時計の針が午後7時を指すと、新木場STUDIO COASTはこの日の最後の出演者を迎えた。蜉蝣である。場内の空気は、あらかじめ普通ではなかった。が、1曲目の「絶望にサヨナラ」で、ドラムを叩く静海の前に設置されたアクリルスクリーンに等身大の大佑の姿が浮かびあがると、けたたましいほどの歓声と、彼の名を絶叫する怒号のごとき響き、感嘆のどよめきが入り交じったノイズがその場を支配することになった。しかし実際、信じがたい光景だった。まるで大佑がそこに居るかのように演奏が繰り広げられ、彼に手を触れようとするかのように観衆のベクトルが前だけを向いていたのだから。 「君らも僕らも大佑も、また出会う。またみんな揃ったら、いつかやろうよ。解散してるバンドだけど、またそのときは蜉蝣でやろう!」 ユアナと静海については無言のままだったが、『漆黒の光』という作品にとっての陰の立役者でもあるベーシストのkazuが客席にそう呼びかけたとき、あちこちからすすり泣く声が聞こえた。が、それは絶望や悲嘆の涙ではなかったはずだ。たった2曲という蜉蝣のステージは、ゲスト・ヴォーカリストを呼び込むことも、映像を使用することもせずに、3人のメンバーだけで演奏された「縄」で着地点を迎えた。ヴォーカルを務めるのはオーディエンスだ。「みんなの歌声を大佑に届けてやって!」というkazuの願いは、間違いなく現実のものとなったはずである。しかもメンバーたちがステージから去ったのち、退場を促す場内アナウンスが繰り返されても、ほぼすべてのオーディエンスがその場を動こうとしなかった。そんなときに場内に流れていたのが、「妄想地下室」。誰かの指揮に従うまでもなく、観衆はそのメロディに声を載せた。そしてその曲が終わった瞬間、この日のライヴは完全に終了に至った。 悲鳴に近い声が飛び交うなか、温かい拍手が自然発生していた。スクリーンには「大佑Forever」という文字が浮かんでいた。そのあまりにもシンプルな言葉が、ストレートに真実を伝えていた。大佑は失われてしまったのではなく、永遠の存在になったのだということを。そして今でも僕の両耳の奥には、彼の「蜉蝣しなさい」という声がこびりついている。それを消去しなければならない理由など、何ひとつないはずなのだ。 文●増田勇一/撮影●河井彩美 |










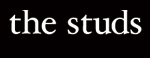




 2010年7月15日、大佑が永遠の眠りについた。そのときの悲しみからいまだに解き放たれていない、という人たちもおそらくたくさんいることだろう。が、それからちょうど1年を経た2011年の同じ日、彼を主人公とする物語に新たな1ページが書き加えられることになった。題して『漆黒の光』。彼の他界後、仲間たちの尽力によって完成に至らしめられた大佑と黒の隠者達にとっての唯一のアルバムと同じタイトルが掲げられた、一周忌追悼公演である。その会場となった東京・新木場STUDIO COASTは、終日、異様な熱気に包まれることになった。平日の午後、早い時間帯からという異例の公演でありながら、チケットは事前に完売。フロアをぎっしりと埋め尽くしたオーディエンスは、故人と所縁の深い出演者たちによる真摯で熱のこもった演奏を、約6時間にわたって堪能しながら、天上の大佑に向けて改めて哀悼の気持ちを伝えることになった。
2010年7月15日、大佑が永遠の眠りについた。そのときの悲しみからいまだに解き放たれていない、という人たちもおそらくたくさんいることだろう。が、それからちょうど1年を経た2011年の同じ日、彼を主人公とする物語に新たな1ページが書き加えられることになった。題して『漆黒の光』。彼の他界後、仲間たちの尽力によって完成に至らしめられた大佑と黒の隠者達にとっての唯一のアルバムと同じタイトルが掲げられた、一周忌追悼公演である。その会場となった東京・新木場STUDIO COASTは、終日、異様な熱気に包まれることになった。平日の午後、早い時間帯からという異例の公演でありながら、チケットは事前に完売。フロアをぎっしりと埋め尽くしたオーディエンスは、故人と所縁の深い出演者たちによる真摯で熱のこもった演奏を、約6時間にわたって堪能しながら、天上の大佑に向けて改めて哀悼の気持ちを伝えることになった。


